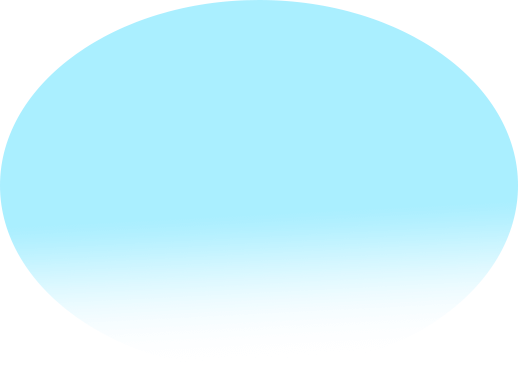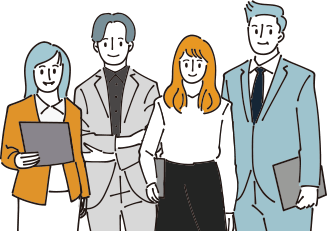当社ホームページの更新日となりました。
今月は一年の半分ペースにあたる6月となります。この時期は梅雨前線が雨をもたらす時期となり、明けると気温がガラっと夏の気候に様変わりする、春と夏の間の時期だと実感します。
そんな6月ですが、昔の日本では「水無月」という用語で呼ばれておりました。
梅雨で雨が沢山降るのに水、無、月というのも変な話ですが、由来は水月の異名であるとか、田端の水を引く時期だからなど諸説が様々あります。
また、この時期、神社では災いや穢れを払う時期とされており、夏越の祓 (なごしのばらえ)と言われています。
この時期に神社に行くと、茅という植物で作られた大きな輪が置かれていることが多いです。
人がくぐれるくらいのサイズで目を引くので、置いている時期まで知らなかったけれどなんとなくイメージが湧く人もいるかもしれません。
昔の人々も、この水無月の時期と以前と以後で気候が大きく変わる事、ちょうど年の半分である事を実感して行事に参加していたのかもしれません。
また、この時期の京都では、そんな時期限定で食べられるお菓子があります。
その名もずばり「水無月」です。
水無月は、三角形の形状をしており、外郎(ういろう)の白い生地に上部分には小豆が乗っている和菓子です。
この形状と色は、一説には氷を模して見た目に涼しさを演出するためなどと言われており、小豆が使われているのも、節分の豆まきのように、厄除けの意味合いで使用されているといわれております。
水無月はこの時期の京都の和菓子屋で売っている事が多いです。
外郎なので、食感はモチモチした弾力があり、上部分は小豆と糖でシャリシャリとした違う食感が楽しめます。
まるで砕いた氷を食べているかのような食感と、半透明の外郎の見た目が涼し気なので、昔の人はこのお菓子を食べて無病息災を願い、夏の暑さを乗り切ろうとしたのだと感じ取れるかもしれません。
この時期は、梅雨入りと低気圧と急な気候の変動で体調が芳しくない人も多いかと思われます。
上記のように、無病息災を願って半年を乗り切ろうとする行事がある事や、
お菓子にも厄払いや涼を見いだそうとする昔の人々の行動からにも、
本格的な夏の時期の前にどう過ごすかというものが、いかに大事かが見えてくるかと思います。
2025.06.16
ブログ